
通常、目に入ってくる光は角膜と水晶体を通じて屈折し、網膜に焦点を合わせます。
この状態を「正視」と呼びますが、ピントが正確に合わない状態を「屈折異常」と言います。
屈折異常は大きく分けて「近視」「遠視」「乱視」の3つの種類があります。
Refractive
近視
近視とは
近視は、眼球が通常よりも長くなっているため、目に入った光が網膜の前で焦点を結ぶ状態です。
近くのものは見えやすく、遠くのものがぼやけて見えます。
近視の発症には「遺伝的要因」と「環境的要因」の両方が関与しており、近年ではパソコンやスマートフォン、タブレットの普及により、子どもたちが近くを見続ける時間が増え、近視人口の増加が予測されています。
日々の生活の中で近視とどう向き合うかが、今後さらに重要になってくるでしょう。
近視が将来の目の病気に与える影響
近視はメガネやコンタクトレンズによって視力を補正できるため、これまで大きな問題として認識されていませんでした。
しかし、近年近視が将来他の目の病気のリスクを高めることが明らかになっています。
特に「黄斑変性」「緑内障」「網膜剥離」などの病気の発症リスクが高まることがわかっています。
例えば、緑内障のリスクは、近視がある場合はない場合と比較して約4倍も高くなるとされています。
強度近視(病的近視)
強度近視(病的近視)とは
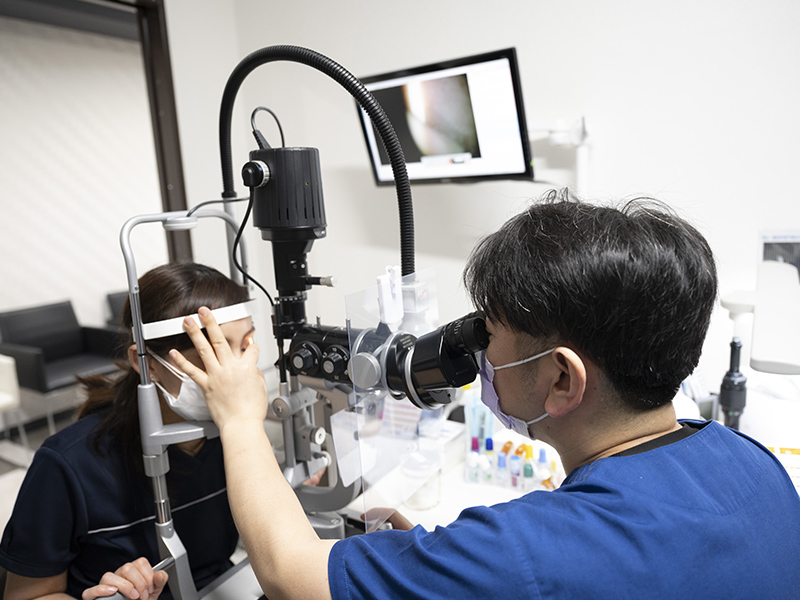
通常、眼球の長さ(眼軸長)は約24mmとされていますが、この眼軸長が異常に長くなる状態を強度近視と呼びます。
強度近視は、近視の度数が-6.00D以上の場合に分類され、眼球の後ろの部分が変形し、網膜や脈絡膜、視神経に病的な変化を引き起こすことがあります。
その結果、視力を矯正しても十分な視力が得られない状態が病的近視です。
強度近視(病的近視)は、日本を含む先進国で中途失明の主な原因の一つとされており、特にアジア諸国で多く見られるのが特徴です。
強度近視に伴う合併症

強度近視は、視力の低下だけでなく、さまざまな合併症を引き起こす可能性が高く、日本の失明原因の上位にランクされています。
主な合併症には以下のものがあります。
近視性牽引黄斑症
近視が進行することで眼球が前後に伸び、網膜が引っ張られて少しずつ層が裂けることを網膜分裂と言います。
初期段階では自覚症状がないことが多いですが、進行すると視力が低下し、最終的には網膜剥離や黄斑円孔などの重篤な目の病気に繋がります。
これらの症状が発生した場合は、網膜硝子体手術が必要となり、硝子体を摘出し、疾患に応じた処置を行います。
近視性脈絡膜新生血管
眼球が引き伸ばされることで、ブルッフ膜に亀裂が生じ、そこから異常な血管が網膜に侵入します。
この血管は脆く、破れて出血し、視力に重大な影響を与えます。
治療としては、「抗VEGF薬」を硝子体内に注射し、新生血管の成長を抑制し、出血を防ぎます。
近視性視神経症
強度近視によって眼球が伸びることで、視神経や視神経線維が引き伸ばされ、視野に障害をもたらす疾患です。
緑内障と似た症状を示し、視野が欠けたり狭くなったりします。
治療としては、眼圧を下げるための点眼治療が行われますが、これはあくまでも進行を抑えるための対症療法です。
一度欠けてしまった視野は元には戻らないため、強度近視の方は定期的な視野検査を行い、早期発見と治療が重要です。
Refractive
遠視
遠視とは
遠視は、眼球が通常よりも短く、目に入ってきた光が網膜の後ろで焦点を結ぶ状態です。
このため、近くも遠くもピントが合わず、全体的にぼやけて見えます。
「遠視」という名称から遠くが見えやすいと誤解されがちですが、実際には遠くも近くも見えにくい状態です。
遠視は、近くを見るときも遠くを見るときもピントを合わせようと目が頑張り続けるため、眼精疲労を引き起こしやすくなります。
特にお子様の遠視は注意が必要です。
生まれつき視力が弱いお子様は、見えにくい状態を当たり前と感じてしまうことが多く、日常生活に不便を感じていないように見える場合でも、視力測定をすると十分な視力が出ていないことがあります。
この状態が続くと、「弱視」や「遠視」に繋がる可能性が高くなります。
外見からは判断が難しいため、3歳児健診や学校健診での眼科検診をきちんと受けることが重要です。
遠視の種類
遠視には、「軸性遠視」と「屈折性遠視」の2種類があります。
人によっては、これらの原因が複合的に作用する場合もあります。
軸性遠視
軸性遠視は、眼軸が通常よりも短いことが原因で起こります。
眼球の奥行きは「眼軸」と呼ばれ、通常は24mm程度とされています。
眼軸が短い場合、光が網膜よりも後ろで焦点を結ぶため、軸性遠視となります。
屈折性遠視
屈折性遠視は、角膜や水晶体の屈折力が不足していることで起こります。レーシックなどの近視矯正手術後や、白内障、翼状片、外傷などが原因で、水晶体が不安定になる場合に発生します。
遠視と老眼の違い
遠視と老眼はよく混同されがちですが、これらは異なる仕組みで起こります。
遠視は、遠くを見るときに屈折異常が生じる状態であり、老眼は、加齢により水晶体の弾力が低下し、近くを見る際にピントが合いにくくなる状態です。
どちらも目の疲れやすさに繋がりますが、それぞれの対応方法が異なります。
Refractive
乱視
乱視とは
乱視とは、角膜や水晶体が歪んでいるために、光が正しく屈折せず、入射する方向によってピントがずれてしまう状態です。
これにより、物が二重に見えたり、ぼやけたりすることがあります。
乱視の種類
正乱視
正乱視は、角膜や水晶体が特定の方向に歪んでいることで起こります。
縦方向や横方向のカーブが異なるため、光が屈折し、焦点が規則的に合わなくなります。
このタイプの乱視は、メガネや乱視用コンタクトレンズを使用して矯正することが可能です。
不正乱視
不正乱視は、角膜の表面が不規則に歪んでいるため、光が正しく屈折せずに、複数の焦点が生じてしまう状態です。
これにより、安定した視界を得ることが難しくなります。
このタイプの乱視は、円錐角膜や角膜変性疾患、外傷などが原因で発生します。
不正乱視の場合、メガネやソフトコンタクトレンズでは矯正が難しいため、ハードコンタクトレンズが必要となります。

